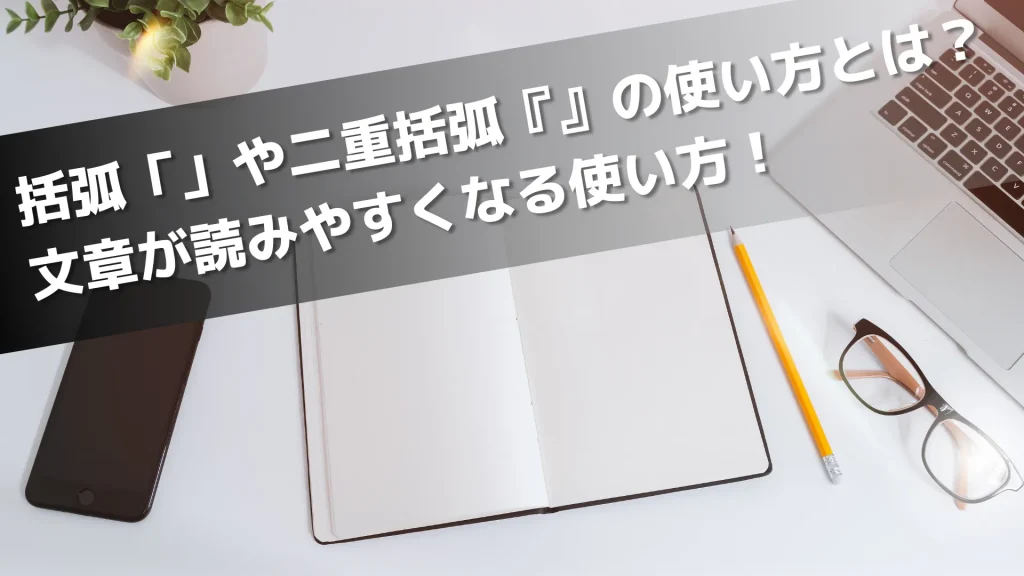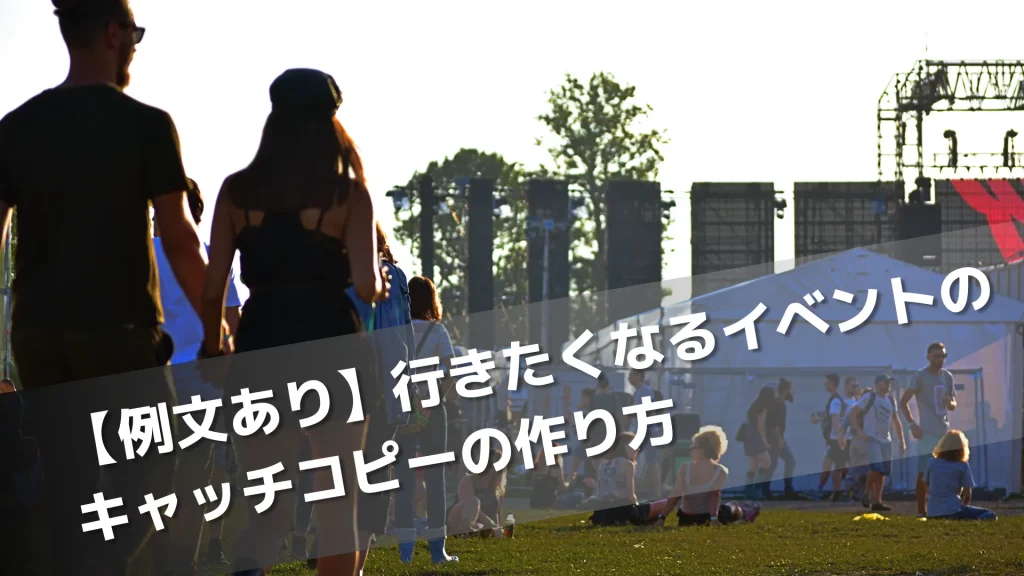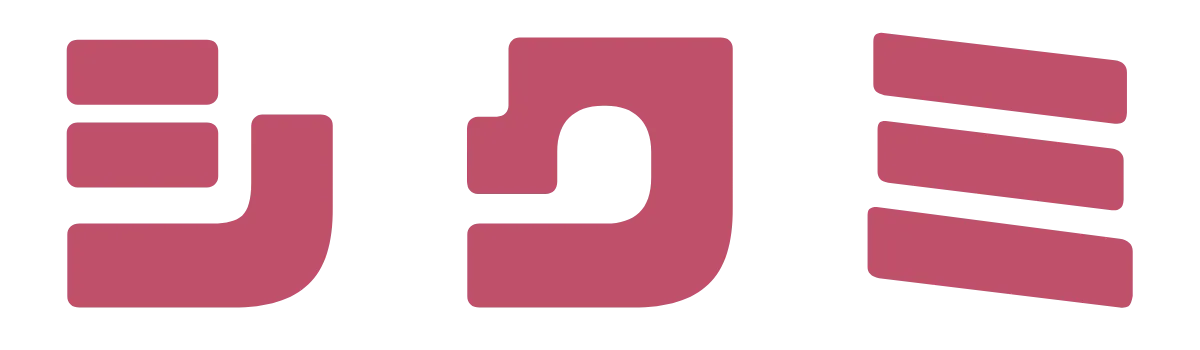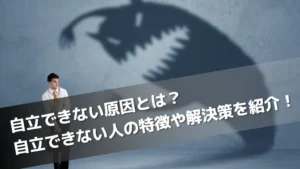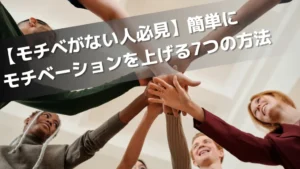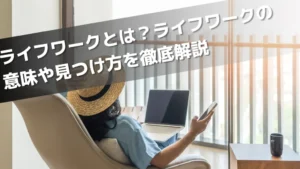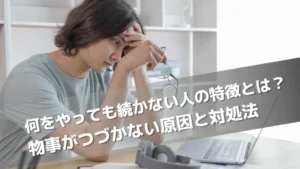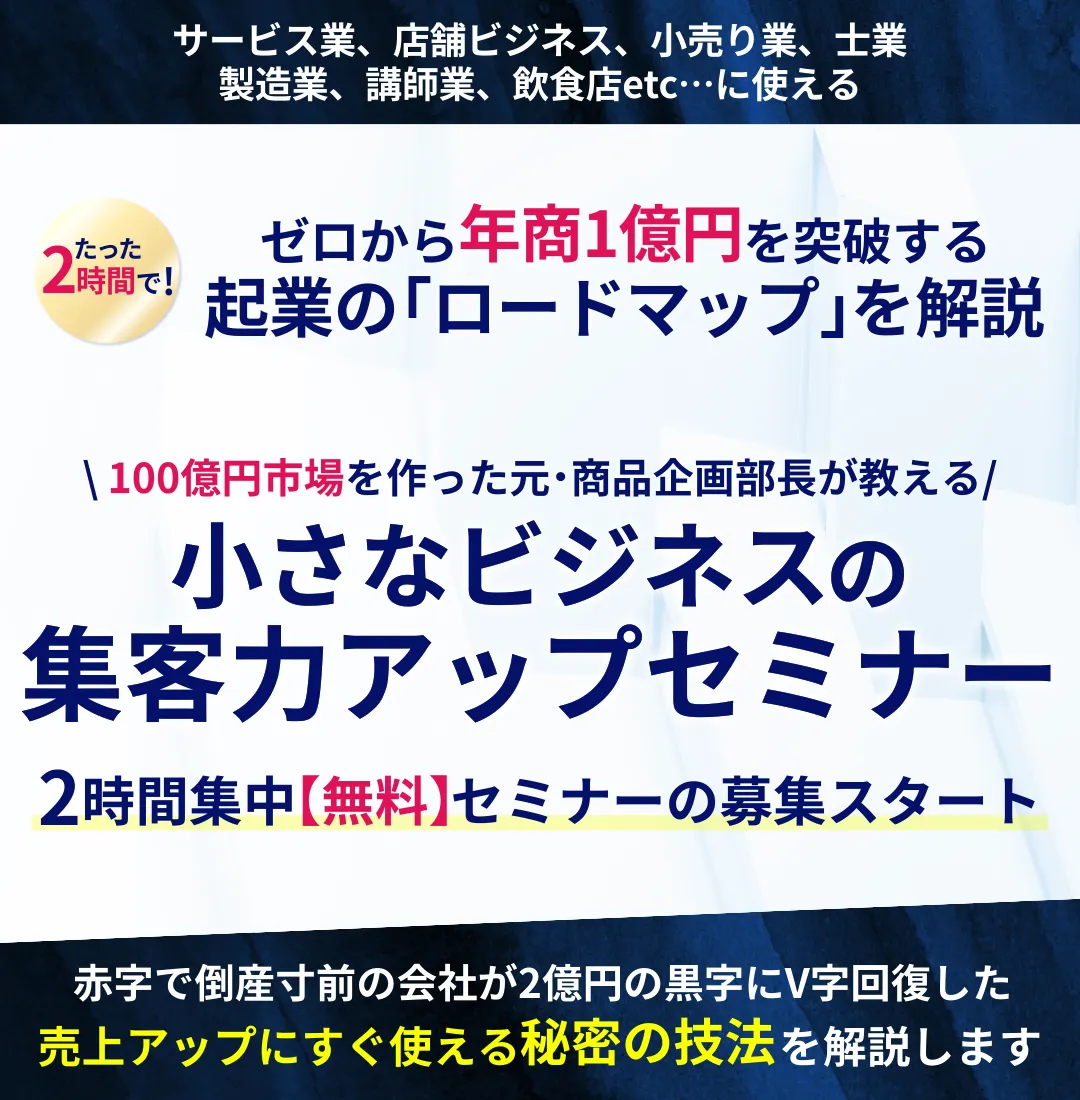
両面提示の法則とは?心理学的な意味や実験例について簡単にわかりやすく解説
- そもそも両面提示の法則って何?
- 両面提示の法則を使うときのコツが知りたい!
- 商品の良さを効果的に伝えるために両面提示の法則は使える?
CMや商品紹介などでマイナスのことを言っているのに、なぜか説得力があり印象に残った経験はないでしょうか?
これはマイナス面とプラス面の両方を伝えることで、信頼感や好感度、説得力が高まる両面提示の法則が働いているからです。
相手への伝え方次第で交渉が上手くいったり、効果的に商品をアピールすることができるわけですね。
ここでは両面提示の法則の心理学的な意味を解説するとともに、CMの事例を紹介しながらビジネスや日常生活で印象を良くする言葉の伝え方を紹介します。
この記事を最後まで読んでいただければ、両面提示の法則を理解し、ビジネスや日常生活で役立つはずですよ。
両面提示の法則とは?心理学的な意味を解説


ビジネスや人間関係において、いい面と悪い面の両方を伝えて相手を説得することを「両面提示の法則」と言います。
あるモノや約束事において、いい面だけを聞いていても「本当に?」と疑ってしまうことはありませんか?
「うまい話には裏がある」という表現もあるように、人はいい面ばかりを提示されると「悪い面を隠しているのではないか」「何か悪い面があるに違いない」と思ってしまうのですね。
しかし、あらかじめ悪い点も説明してくれると、誠実さが伝わり、信用度が上がります。
さらに、リスクに合意しての行動に繋がるので、後からトラブルになることがありません。
たとえば、商品やサービスの特徴を時間をかけて伝えることでユーザーを購買行動に導くインフォマーシャルという手法があります。
このインフォマーシャルの生みの親である全米屈指のコピーライター、ジョセフ・シュガーマンも、欠点を告白することで購買意欲を高める手法をマーケティングに用いていたのですね。
いい面と悪い面の両方を伝えることで信頼感や説得力が上がるので、両面提示の法則はマーケティングにおいても非常に効果的なのですよ。
次に実験例をみながら両面提示の法則が効果的な理由について、さらに詳しく見ていきましょう。
実験例から考える両面提示が効果的な理由とは?


では、なぜ両面提示がコミュニケーションにおいて重要な役割を果たすのかについて見ていきましょう。
たとえば、東京工業大学では広告のリスクコミュニケーションの影響に注目し、広告の商品を生命保険にスポットを当て、広告の効果と比較実験が行われました。
実験では情報を積極的に提供するリスクコミュニケーションを取り入れることで広告の効果が高くなることが証明されました。
また商品に対する実験では、生命保険の商品説明をする際に、商品のプラス面だけを説明する場合と、マイナス面を含めて説明する場合の比較実験がおこなわれました。
この結果、8割の学生が商品のマイナス面についても説明を受けた方が「好感が持てる」と回答しました。
この実験から分かるように、両面提示がビジネスコミュニケーションにおいて効果的な理由は2つが考えられます。
ここでは、この2つの理由について詳しく見ていきましょう。
※1 東京工業大学 社会心理学研究「広告におけるコミュニケーションの影響-生命保険の場合-」
理由①デメリットが好感につながるから
両面提示が効果的な理由の1つ目は「デメリットが好感につながる」からです。
先ほどの生命保険の実験結果からもわかるように、両面提示をすることで広告に対して好意を持つ人が多くなります。
たとえば、生命保険の場合加入する場合のメリットとデメリットは以下のようなものです。
| メリット | ・万が一の保障 ・相続税対策 ・所得税・住民税軽減 |
|---|---|
| デメリット | ・インフレリスク ・保険料 ・すぐに解約すると損 |
このように生命保険にはいくつかのデメリットがありますが、事前にデメリットを打ち明けることで「誠実で信頼できる」という印象を受けるのです。
私の母は現役で保険の営業の仕事をしています。
初めの契約こそはデメリット、特に保険料等で苦戦することもあるようです。
しかし、加入したお客さんが保険を使わなければいけなくなったとき「保険をかけていて良かった」と感謝され、次につながることもあるそうです。
生命保険の例に限らず、あらゆる商品やサービスにはデメリットが必ずあります。
なので、あなたがセールスマンであるならば、商品やサービスを説明するときにメリットとデメリットの両面を提示することで、あなたは顧客から好感を得ることができるのです。
理由②説得力が増すから
両面提示が効果的な理由の2つ目は「リスクコミュニケーションが説得力を増す」からです。
いい面と悪い面の両方を伝えることで、相手は本当のことを言ってくれていると感じ信頼感が増します。
信頼できる相手からの情報は説得力がありますよね。
さらに「高いけど性能がいい」のようにメリットを裏づけするようなデメリットならば、より説得力が高まります。
また、リスクに関する情報を関係者同士で共有し理解を深めることで納得して意思決定をするので、後になって「知らなかった!」「聞いていない!」となる可能性も少なくなります。
つまり、トラブルやクレームを回避し、リスクマネジメントができるのですね。
説得力を高め、リスク回避ができるのも両面提示の法則の大きな効果と言えますよ。
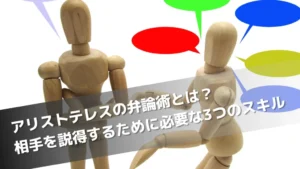
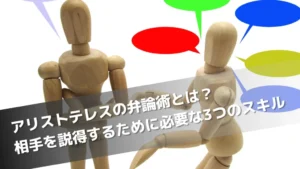
両面提示の法則で押さえておくべき2つのコツ
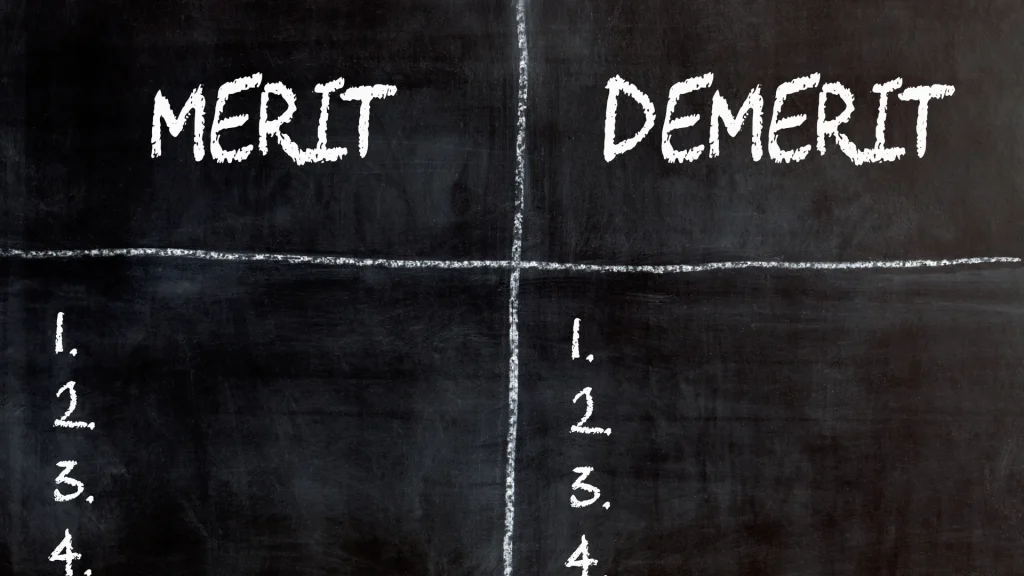
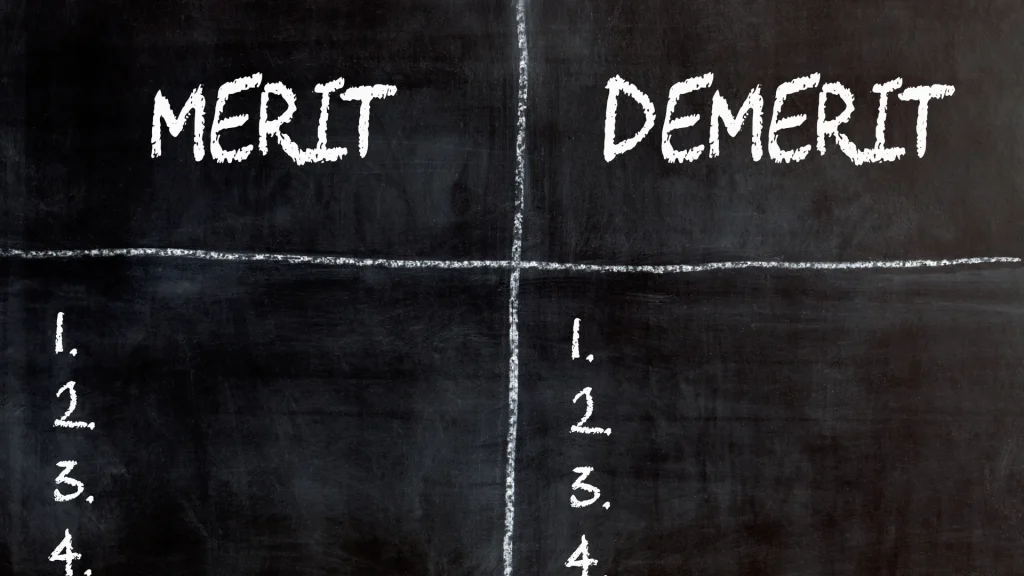
「両面提示の法則」とはメリットとデメリットを両方提示することで相手の信頼感を得るのに効果的です。
しかし、ただ単にメリットとデメリットを伝えればいいわけではありません。
両面提示の法則をより効果的に活用するためには、押さえておくべきコツが2つあります。
ここでは、メリットとデメリットを伝える順番や何を意識すると良いかを解説していきます。
コツ①伝える順番は「デメリット」「メリット」の順にする
両面提示の法則を使う際、「デメリット」と「メリット」どちらを先に伝えるべきでしょうか?
答えは、“デメリットは先に、メリットは後に伝える”です。
なぜなら、「人は最後に与えられた情報で印象が決定されやすい」という親近効果の心理が働くからです。
たとえば、商品を説明する際の伝え方を比べてみましょう。
- 「この商品は性能がいいけど、高い」
- 「この商品は高いけど、性能がいい」
デメリットを先に伝えてから後からメリットを伝える後者の方がいい印象を持ちますよね。
デメリットがメリットにより打ち消されているのです。
もちろん場面により異なりますが、商品の案内やプレゼン、自己PRなど相手にいい印象を残したい場合はメリットを後から伝えるとより効果的ですよ。


コツ②ポジティブなデメリットを意識する
メリットだけではなくデメリットも一緒に伝えるのが両面提示の法則ですが、デメリットを伝える時に意識すべきことがあります。
それはポジティブなデメリットを相手に伝えるという点です。
例えば、商品を購入する際に「即日納品できない」と言われると「すぐには対応が出来ない」という面でデメリットを感じますよね。
しかし、「安心してお使いいただくためにしっかり検品をしてから発送するので、即日納品できない」と言い換えれば印象が良くなります。
つまり、ポジティブなデメリットを意識することで、デメリットがメリットにも感じられるのですね。
ただし、デメリットが大きすぎるとお客さんに買ってもらえないという問題も出てきます。
そのため、表現や手法を意識しながらポジティブなデメリットを伝えることが大切ですよ。
【実例】両面提示の法則を活用しているCMを紹介


私たちの身近にも、両面提示の法則を使って視聴者を上手くひきつけたCM(コマーシャル)があります。
「初めての方にはお売りできません」
「まずい、もう一杯!」
誰もが一度は耳にしたことがあるフレーズではないでしょうか?
この2つのCM事例を取り上げ、両面提示の法則で成功した秘訣をひも解いていきます。
例①ドモホルンリンクルのCM「初めての方にはお売りできません」
ドモホルンリンクルは1974年に再春館製薬所が開発した基礎化粧品です。
ドモホルンリンクルのCMでは「初めての方にはお売りできません」という商品を売る企業らしからぬ言葉が使われました。
本来であれば、作った商品をお客さまに購入してもらいたいと考える企業がほとんどですよね。
しかし、ドモホルンリンクルでは、あえて初めての方には売らないという制約(デメリット)を伝えています。
試供品を使ってもらい、化粧品の効果に納得してもらったお客さんにだけ購入をしてもらうのですね。
そうすることで、本当にお客さんのことを考えていいものを提供しているのが伝わり、商品に対する信頼感が生まれます。
さらにお試しで納得した上で化粧品を購入するので、購入後のトラブル減少にも繋がったのです。
両面提示の法則を使うことによって、ドモホルンリンクルに対する信頼感や好感が増した成功例と言えますね。
例②キューサイの青汁「まずい、もう一杯!」
キューサイの青汁のCMも両面提示の法則をうまく活かしている例です。
キューサイの青汁は、CM内で食品を「まずい」とあえて言うことで大きなインパクトを残しました。
多くの人は青汁は健康に良さそうだけど、まずそうと思っていますよね。
この「まずい」というデメリットをあえて言うことで信用度が増します。
だからこそ「もう一杯」飲みたくなるほど身体にはすごくいいというメリットの信憑性も高くなってユーザーにいいものであることが伝わるのですね。
また、「まずい」とデメリットを最初に伝えておくことで、ユーザーもあらかじめ味の想定ができるので後から「まずい」というクレームを避けることができます。
味は「まずい!」けど、それ以上に健康やお肌の改善に効果抜群という自信があるからこそ考え出されたフレーズと言えますね。
「両面提示」と「片面提示」の違いとは?


これまでに事例などを交えて紹介してきた両面提示は、メリットとデメリットの両方を伝える方法でした。
この両面提示と反対の意味を持つのが「片面提示」です。
片面提示とはメリット・デメリットのどちらか一方だけを伝える方法で、相手が提案に対して何も知らないときや、提案に興味を持っている場合などに有効です。
両面提示と片面提示を使うときは、交渉する内容や交渉相手との関係性によって使い分けるようにしましょう。
なぜなら、間違った使い方をすると効果を発揮しないだけではなく、トラブルを招く可能性もあるからです。
特に、片面提示は信頼関係がない相手に使うと不信感が増す原因にもなるので注意が必要です。
たとえば、ある商品についてのメリットしか聞いていなかった場合、後になって問題やデメリットが生じると「聞いてなかった」「教えてもらっていない」とクレームに発展する可能性が高くなりますよね。
すでに商品に興味を持っていたり、相手との間に信頼関係がある場合の最後の一押しとして片面提示を使うのがいいでしょう。
逆に、商品について知ってほしい場合や信頼関係を築きたい場合などは断然「両面提示が有利」だと言えますよ。
そして両面提示を行うことで得られる顧客との信頼関係構築には、ラポール形成することも大切です。ぜひこちらからラポールについてご覧ください。
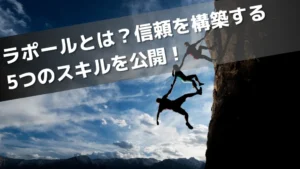
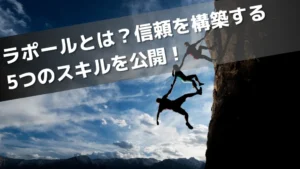
まとめ
いかがでしたか?この記事ではビジネスや人間関係で使える「両面提示の法則」について様々な角度で解説してきました。
まとめると
- メリットとデメリットの両方を伝えて説得するのが両面提示の法則
- 両面提示が有効な理由は、デメリットが好感になり説得力が増すから デメリットを先に伝えることとポジティブなデメリットを意識することが両面提示のコツ 商品の魅力を伝えたい場合は「片面提示」よりも「両面提示」が有効
「両面提示の法則」について理解を深め、正しく活用することが出来ればビジネスにおいて非常に役立ちます。
この記事を参考に、効果的な伝え方を意識してみてくださいね。