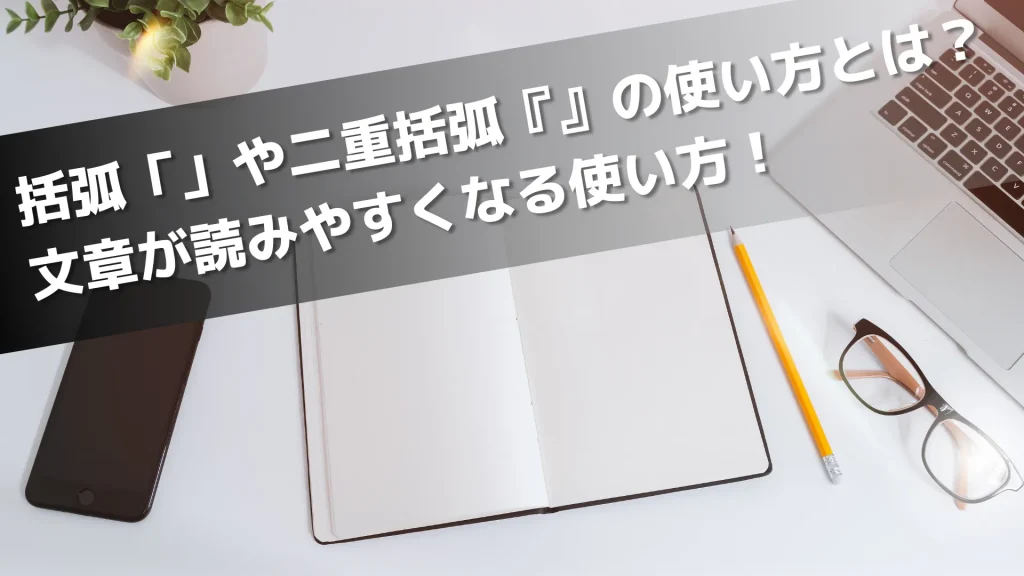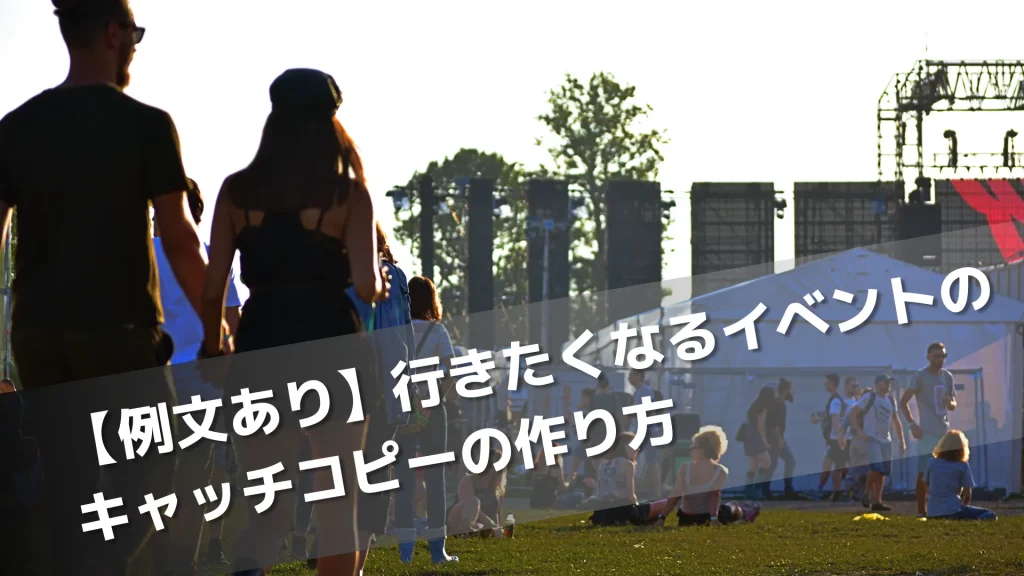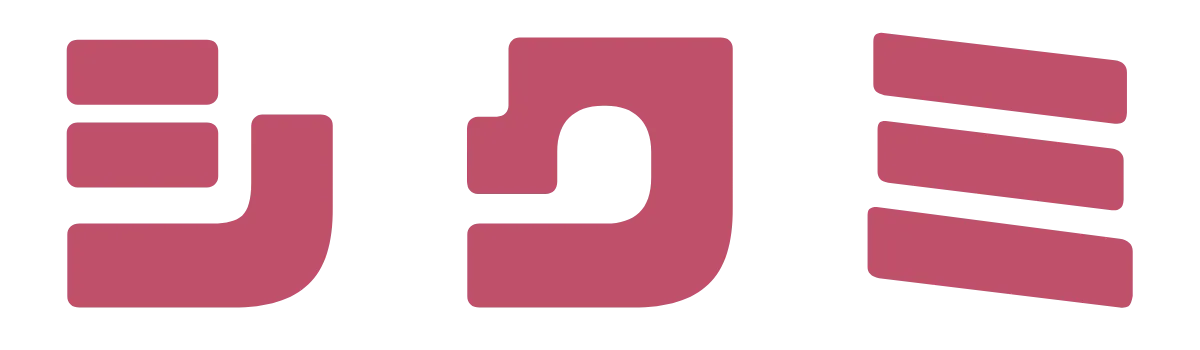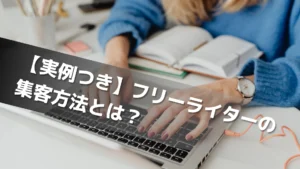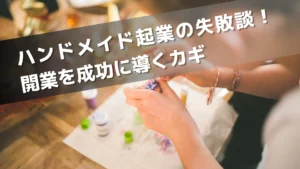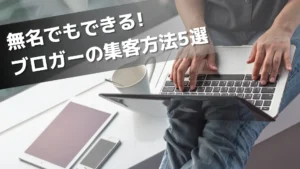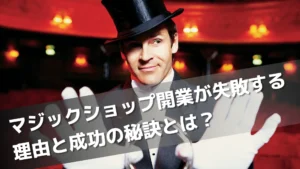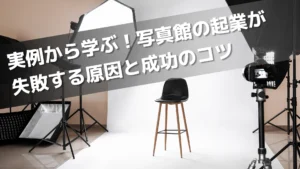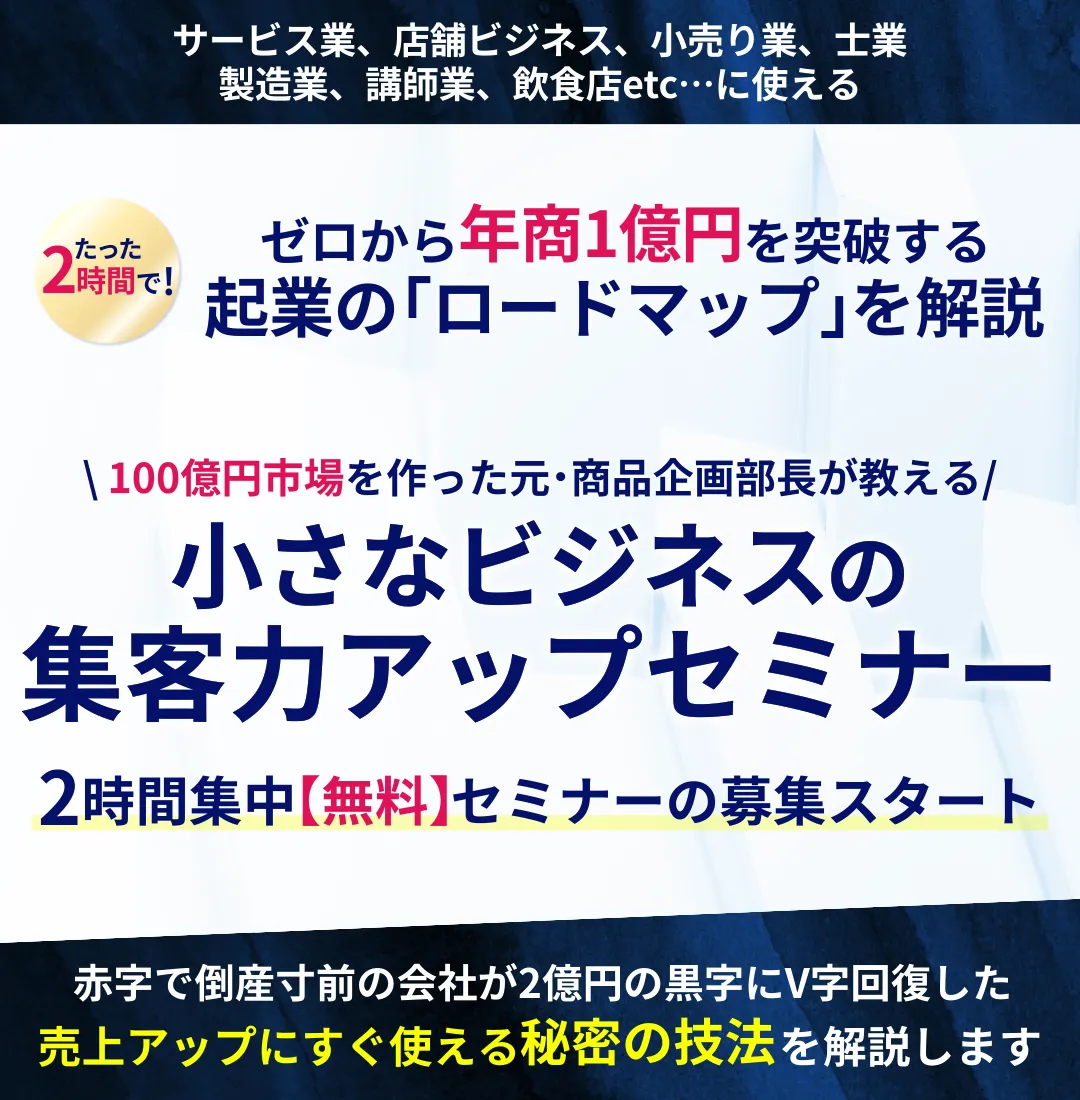
リフォーム会社の開業は儲かる?独立起業の実例から学ぶ失敗と成功のワケ
- 職人として自分の技術を活かしてリフォーム業で起業したい!
- リフォーム業で独立したいけど何から始めたらいいのかわからない
- 長く需要があるリフォーム業は安全に起業できそう!
ここ数年、生活スタイルの幅が広がり、住まいへの関心は高まっていると言われています。
その中でも、空き家を利用した中古住宅流通や、リモートワーク環境対応によるリフォームなども影響し、リフォーム業界の需要は今後さらに高まるだろうと予想されています。
そのため、これを機に開業を考えている方も多いのではないでしょうか。
今回は、リフォーム会社の開業についての成功のポイントをまとめていきます。
闇雲に開業するのではなく、しっかりポイントを押さえておけば、経営を安定させることができますよ。
確かな技術と経営のノウハウで、顧客から長く愛される会社を目指しましょう。
リフォーム会社の独立開業で失敗した事例


今回紹介するのは、差別化を意識しすぎて利益が出ず経営が立ちいかなくなった事例です。
注目を集め、名前をおぼえてもらうために「差別化」というのは確かに必要な戦略の一つですよね。
しかし、低価格という利益に直結する差別化を選択することには注意が必要です。
「自分が同じ立場で起業するとしたら」という気持ちで読み進めて、失敗の経緯や改善策について一緒に考えてみましょう。
工務店勤務から独立で失敗に至った経緯とは?
起業するまでは工務店に勤めていましたが、約16年勤めている間に工務店での仕事は一通り身に付いたので独立したいと思っていました。
時代と共に工務店の仕事量が目に見えて減っていたので、先を見越してリフォーム業を立ち上げようと考えました。
この先日本は国民の半数以上が高齢者となるのでバリアフリーなどのリフォームの依頼が多くなり安定した仕事量を確保できると思ったからです。
しかし実際に起業してみると予想以上にライバル会社が多く、契約が取れません。
ライバル会社と差別化するために工事単価を下げてお客さんをゲットしましたが、単価を下げ過ぎて儲けが出なかったうえに材料費の高騰も重なり会社は赤字続きとなりました。
仕方なく単価を上げて黒字を目指しましたが、工事費を上げるとお客さんはまったく寄りつきません。
ブランド力の高い大手のリフォーム会社に流れて行ったのでしょう。
結局さらに赤字は進み会社を維持することができず廃業しました。
※上記は自社の独自アンケート調査をもとに作成したものです。
工務店勤務から独立で失敗した要因は?
一言で言うと会社運営に関する勉強不足と経験不足だと思います。
大手のリフォーム会社と差別化をはかるために工事単価を下げ、お客さんを得ることはできたものの、件数をこなさなければ会社の利益にはなりませんでした。
加えて、国際情勢などの影響で材料費も高騰し材料そのものの確保が苦しい状況でした。
そのため単価を上げることにしたのですが、そうするとお客さんが遠退いてしまいます。
この状況にはじめは戸惑いましたが、結局は私が経営者としての知識や経験がなかったから失敗したのだなと強く思いました。
単価を下げればお客さんは得られますが、安さで差別化を図るべきではなかったです。
※上記は自社の独自アンケート調査をもとに作成したものです。
今回の経験で得た教訓とは?
今回は、他社と比較し過ぎて無理な工事単価で請け負っていたため首が回らなくなり最終的に閉業となりました。
もう一度起業するならば他社を意識せず自身のペースで運営したいです。
よくよく考えると、本当にリフォームを考えている方は工事費を大幅に下げなくても利用してくれると思います。
なので、もう一度起業したら需要を見極めるために徹底的にリサーチをおこない、相場の工事費で請け負いたいです。
何よりも目先の利益に翻弄されず、会社を安定的に運営できるよううまくバランスを取りたいと思います。
※上記は自社の独自アンケート調査をもとに作成したものです。
資格は不要?!リフォーム会社が儲かるといわれている理由


「リフォーム会社が儲かる」といわれている理由は、主に次の3つにあります。
- 参入ハードルが低い
- 空き家の活用や中古住宅の需要が高まることで市場は増加傾向にある
- 家のメンテナンスはどの家庭も必要になるので、常に需要がある
自分に技術があれば始められ、職人とのネットワークなどが確立されていれば少ない資金で開業できるため、参入ハードルが低いといえるでしょう。
また、サステナブルという言葉が広く認知され、空き家の活用や中古住宅が一気に注目を浴びたことで、リフォーム業界にも追い風となっています。
そして、どんな家でも、長く住めばメンテナンスは欠かせませんよね。
こういった一定の需要があるので、安定して仕事が受注できれば勝ち続けることもできるでしょう。
リフォーム会社の独立開業で多い3つの失敗要因


自分に技術があり、多様な案件に対応できても、仕事を取ってくるための経営の知識や営業努力は必要です。
開業のハードルが低く、始めやすいと言っても成功するかどうかは別の問題であることを十分理解しておきましょう。
ここからは、よくある失敗の原因を3つご紹介します。
いざ開業するとなった時に、以下の要因をどうやって回避するか考えながら読み進めてみてくださいね。
失敗要因①経営の知識不足
失敗談にもあるように、経営の知識不足は失敗へ直結してしまいます。
独立・開業では、職人であると同時に会社の経営者になるということをしっかり自覚しましょう。
自分に職人としての技術があり、クオリティの高い施工ができる自信があっても、仕事を受注できなければ利益は発生しません。
名前を知ってもらうための方法や、顧客との信頼関係を構築する営業の努力、経費を管理し利益をあげるための知識は、事前にしっかりと勉強しておく必要がありますよ。
また、リフォーム業に多い一人親方の場合も、現場に出ている時間と事務時間のバランスが取れず経営が立ちいかなくなる場合があるため注意しましょう。
経営の知識がないのであれば、資金はかかってしまいますが、フランチャイズに加盟してそのノウハウや知名度を経営に活かすという方法もあります。
経営の仕組みを理解し、事業の安定だけでなく世の中の変化やトラブルがあった際にも、いち早く対応できる準備をしておきましょう。
失敗要因②受注が少ない
新規の仕事が受注できても、リピートにつながらなければ、全体数が増えていかないため、利益を大きくすることが困難です。
一度きりの依頼になってしまわないよう、顧客との信頼関係を築き、リピーターを獲得することを意識しましょう。
また、リフォームといっても水回りから屋根の修繕までさまざまな種類があります。
どのような施工ができるかを明確に示すことで、顧客の目にとまりやすくなるため、依頼につなげることができますよ。
たとえば「バリアフリーリフォーム専門」で、バリアフリーの施工依頼が軌道に乗れば、この分野の顧客を一定数確保でき、今後の経営の見通しもつきやすくなりますね。
顧客は、直したい所をピンポイントで探していることがほとんどなので、得意な施工やノウハウのある分野はしっかりとアピールしていきましょう。
専門性のアピールで、リピート客の確保し安定した受注の見込みを立てることが大切です。
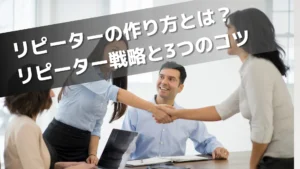
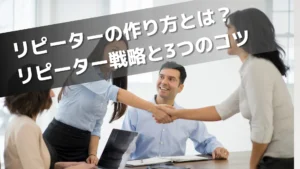
失敗要因③差別化の方法が間違っている
注目を集めたり、他社と比較してもらったりするために「差別化」を図ることは重要ですが、自分の経営スタイルに合った方法をとらなければ失敗の原因となってしまいます。
特に、失敗談にもあった価格の安さで差別化を図ると利益を下げることになるため危険です。
得意な分野をアピールしたり、アフターサービスを手厚くしたり、差別化をおこなう方法は多様にあり、安いことだけが魅力ではありませんよ。
利益を確保したうえで、自分の経営に合った差別化の方法を模索しましょう。
仮に値上げをするなら、言い方や伝え方をしっかりと考える必要があります。こちらの記事で、値上げの仕方について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
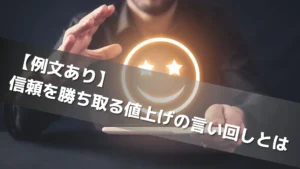
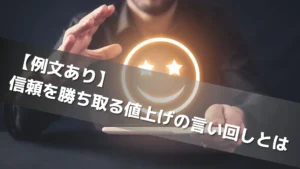
リフォーム会社の起業を成功させる6つのポイント


リフォーム会社の開業を成功させるには、ニーズの把握や、顧客との信頼関係を築くなどで、顧客の方から依頼が来るような流れをつくることが大切です。
また、安定して依頼が取れるよう、ターゲットにあわせた集客をすることも成功への近道になりますよ。
ここからは、リフォーム会社の開業を成功させる6つのポイントを紹介していきます。
ポイントを押さえ、経営の知識や戦略について考えていきましょう。
- ポイント①マーケティングで顧客とニーズを把握する
- ポイント②資格や許可はしっかりアピールする
- ポイント③相談から完成までを見える化する
- ポイント④アフターサービスや保証を充実させる
- ポイント⑤口コミで信頼度を高める
- ポイント⑥一つの業務に特化する
リフォーム業の効果的な集客については、こちらの記事で具体的に解説しているので、参考にしてくださいね。
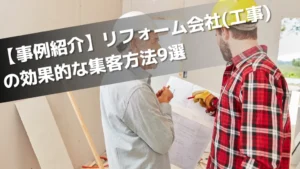
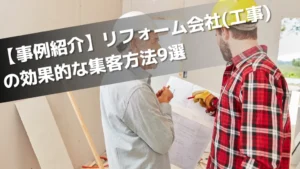
ポイント①マーケティングで顧客とニーズを把握する
開業したい地域でどのようなニーズがあるか把握しましょう。
たとえば、30年前に新興住宅地として開発された地域のニーズを考えるとします。
どの住宅も築30年程度、老朽化した設備の修繕や、いざという時のバリアフリー化などの需要があるのではないかと予想できますよね。
また、新築の頃から住み続けているとすれば、年齢層は50〜70代ということも把握できます。
このようなリサーチから、SNSよりも広告などの紙媒体で住宅のバリアフリー化を案内すると、効果的に集客できる可能性が高いですよ。
「誰にどんな提案をするか」というモデルを具体的に設定することで、ニーズに応じた効果的な集客を目指しましょう。


ポイント②資格や許可はしっかりアピールする
500万円未満の工事を請け負う場合、特別な許可や資格は必要ありません。
しかし、顧客にとって、資格を持っていることは「専門性の高い知識を持ち、安心して任せられるか」を客観的に知るための情報です。
そのため、資格や肩書は重要なアピールポイントになります。
建築業全般で有効な「建築士」を持っていれば、積極的にアピールすることで、顧客の信頼度はグッと上がるでしょう。
また、民間資格でも「インテリアプランナー」という室内空間の設計に長けた資格や、「リフォームプランナー」のような、リフォームに特化した資格も、顧客へのアピールにはおすすめです。
リフォーム業で役に立つ資格は、国家資格から民間資格までたくさんあります。
資格を取得することで、顧客への安心感と同時に自身のスキルアップも目指しましょう。
ポイント③相談から完成までを見える化する
相談から完成までのシミュレーションがあれば、顧客は安心してリフォームを依頼することができます。
ホームページやSNSなどで具体的な料金などを提示した事例を掲載するなど、顧客が業者探しを始めた早い段階でシミュレーションができる工夫をしましょう。
そうすることで「ここに依頼すれば、こんな流れでこんな風に仕上がる」という顧客のイメージが固まり、依頼につなげられますよ。
また、顧客が安心して依頼できるように、契約後の進捗状況の確認や、気になる点をいつでも問い合わせできるシステムづくりも大切です。
大きなお金の動く「リフォーム」というイベントは、頻繁におこるものではありません。
「ちゃんと施工してくれるか」「思い通りに完成するか」など顧客はたくさんの不安を抱えていることを理解し、完成までの過程が見える施工を心がけたいですね。
ポイント④アフターサービスや保証を充実させる
アフターサービスや保証を充実させ、顧客との関係を強化することで、リピーターになったり、新たな顧客を紹介してもらえたり、経営の安定につながります。
リフォームが終わったら関係が終わってしまうのではなく、トラブルや不具合を相談できる長いお付き合いをする体制をととのえましょう。
「困ったことがあればここに頼めば大丈夫」と思ってもらえれば、リピーターとして次の契約の可能性も高まります。
新たな顧客を獲得するには、営業活動にコストがかかりますが、リピーターを獲得できれば少ないコストで収入を獲得することができますよ。
顧客の立場でどんなサービスやサポートがあれば「また頼みたい」と思うかを考えながら一件一件丁寧に対応し、顧客との良好な関係を築いて安定した経営を目指しましょう。
ポイント⑤口コミで信頼度を高める
顧客との良好な関係が築けたら、積極的に口コミをお願いしましょう。
顧客は業者選びをする際、実際のレビューや体験談など、生の声を判断基準にする場合が多いといわれています。
口コミの数の多さはもちろんのこと、良かった点やリフォーム後の写真があれば、事前に不安がやわらげられ、安心して依頼してもらえるでしょう。
ですから、先ほどお伝えしたポイント④のリピーターの獲得も重要です。
既存の顧客との良好な関係を築けると、良質な口コミが増え、新規の顧客へのアピールにつながりますよ。
ポイント⑥一つの業務に特化する
「●●といえばここ!」というような強いアピールポイントでお店の価値を高め、選ばれる経営を目指しましょう。
得意な分野を持つことは、差別化にとても有利です。
また「得意=こだわり」として価値を生むことで、適正な料金設定への後ろ盾にもなりますよ。
ここから、具体的なアピール例を3つ紹介していきます。
【アピール例】バリアフリー専門
「バリアフリー専門」のアピールは、高齢者やその家族をターゲットにするとよいでしょう。
年齢層は50〜80代が多いと予想されることから、ホームページだけでなく、フリーペーパーや広告などの紙媒体でのアピールが効果的と考えられますね。
バリアフリーリフォームは介護保険の適用になるため、リフォーム内容とあわせて、申請の流れについて詳しく知りたい顧客も多いでしょう。
ホームページや広告には保険適応条件の相談を受け付けたり、ケースごとのビフォーアフターを詳しく掲載すると、分かりやすい資料になります。
当事者だけでなく家族で共有できると、意思決定までがはやく、依頼へつながりやすくなりますよ。
バリアフリーでは、高齢者本人のものとしてだけでなく、その家族なども意識したアピールを心がけましょう。
【アピール例】テレワーク向けの内装リフォーム専門
働き方の概念も多様となった現在、テレワークを選択する人も多くなりました。
そのため、現役世代でも自宅で居住スペースとワークスペースを分けるリフォームをしたいと考える方も増えています。
普段からインターネットやパソコンを使う世代が中心となるため、SNSやインターネット広告などでアピールすることで、効率よく集客ができますよ。
また、先ほどのバリアフリーのリフォームとは異なり、テレワークをおこなう本人に向けてのアピールが重要です。
施工の流れももちろんですが、画像やイラストなど完成形のイメージを多く伝えることで、「こんな環境で仕事をする自分」を想像し、関心を持ってもらう工夫をしましょう。
リフォーム後の機能だけでなく「気持ちよく仕事できる満足感」という顧客の感情に訴えるアピールが大切です。
【アピール例】遮熱・断熱リフォーム専門
遮熱・断熱リフォームを専門とする場合は、地域の特性に合わせたアピールを工夫しましょう。
例えば、積雪の多い地域の場合、築年数が長いと冬場は部屋の温度差などでヒートショック現象などが心配されますよね。
断熱リフォームで実際の部屋の温度を比較した事例など、目に見えて結果がわかるアピールをすることで、リフォーム後のメリットを裏付けましょう。
暖房効率など、電気代の比較も効果的ですね。
遮熱や断熱は、窓の機能や壁の裏側など、普段の生活では見えない部分のリフォームです。
数字の出る結果など、しっかりとした根拠を示すことで、リフォームの価値をアピールしましょう。
まとめ
今回のまとめは、以下のようになります。
- リフォーム会社の開業は、参入ハードルが低く始めやすいが、経営者としての知識も必要
- リフォーム業で安定して収入を得るには、顧客を獲得する努力を惜しまない
- リフォームに関する資格や許可、得意分野をアピールし、差別化を図る
- 一つの業務に特化するなど、ターゲットを絞り込んで集客する
リフォーム会社は特別な資格を持たず始められる反面、何かに特化していないと大手やライバルの中に埋もれてしまいます。
また、闇雲に営業をかけても「どんな会社かよく分からない」と判断されてしまい、仕事を獲得できず、結果的に失敗することになります。
自分の会社はどのような施工が得意で、「誰に」「何を」「どう売りたいか」というモデルを明確にすることを大切にしましょう。
職人としての技術だけでなく、経営者としての考え方も備えることで、大きく成長できる会社になりますよ。