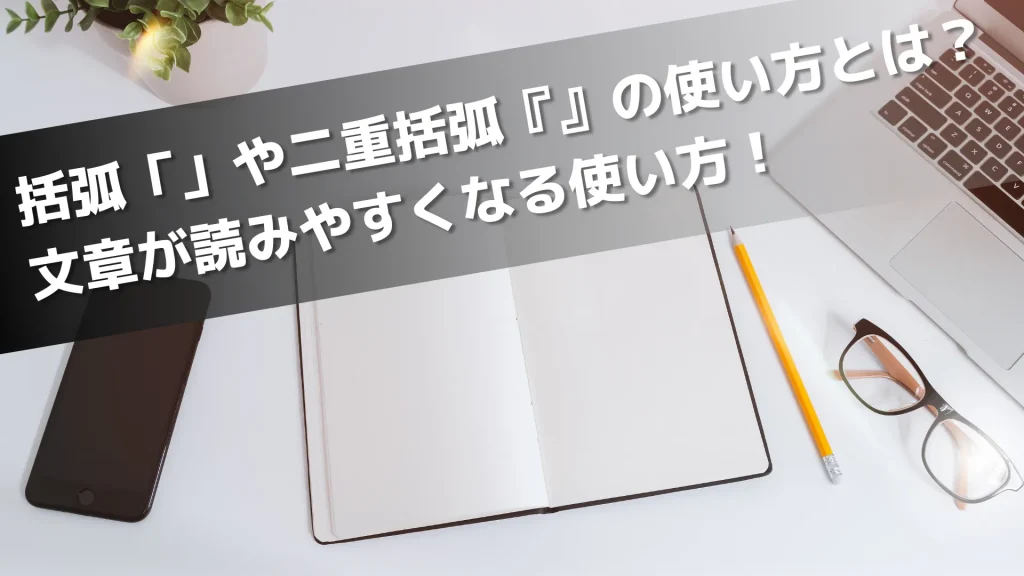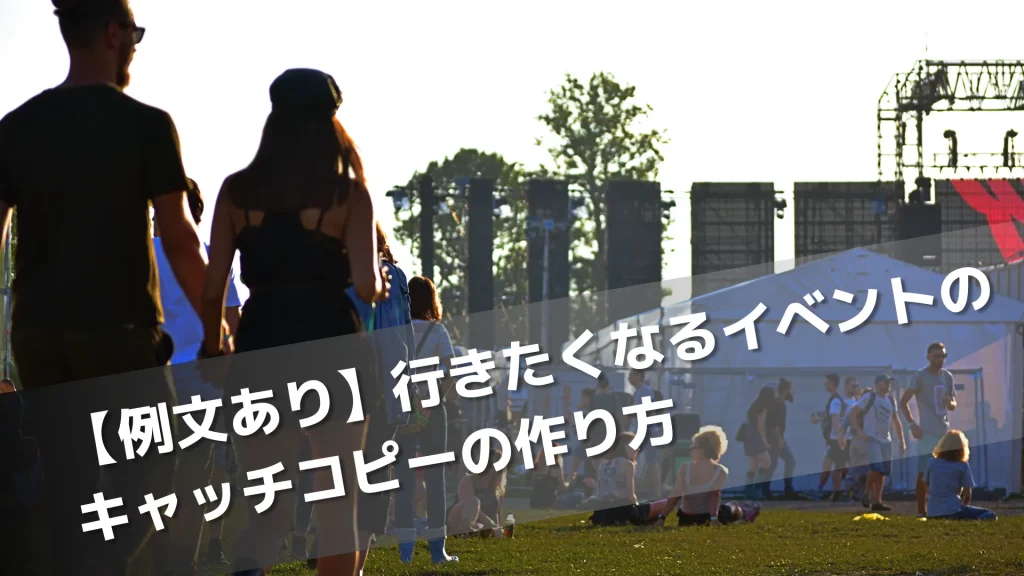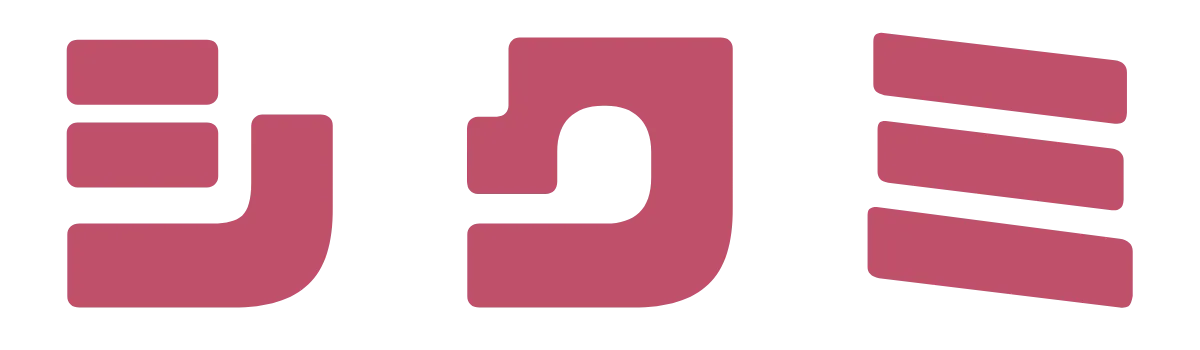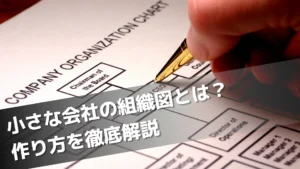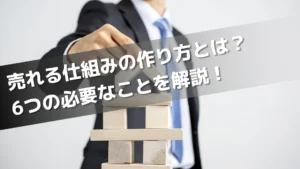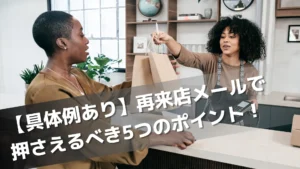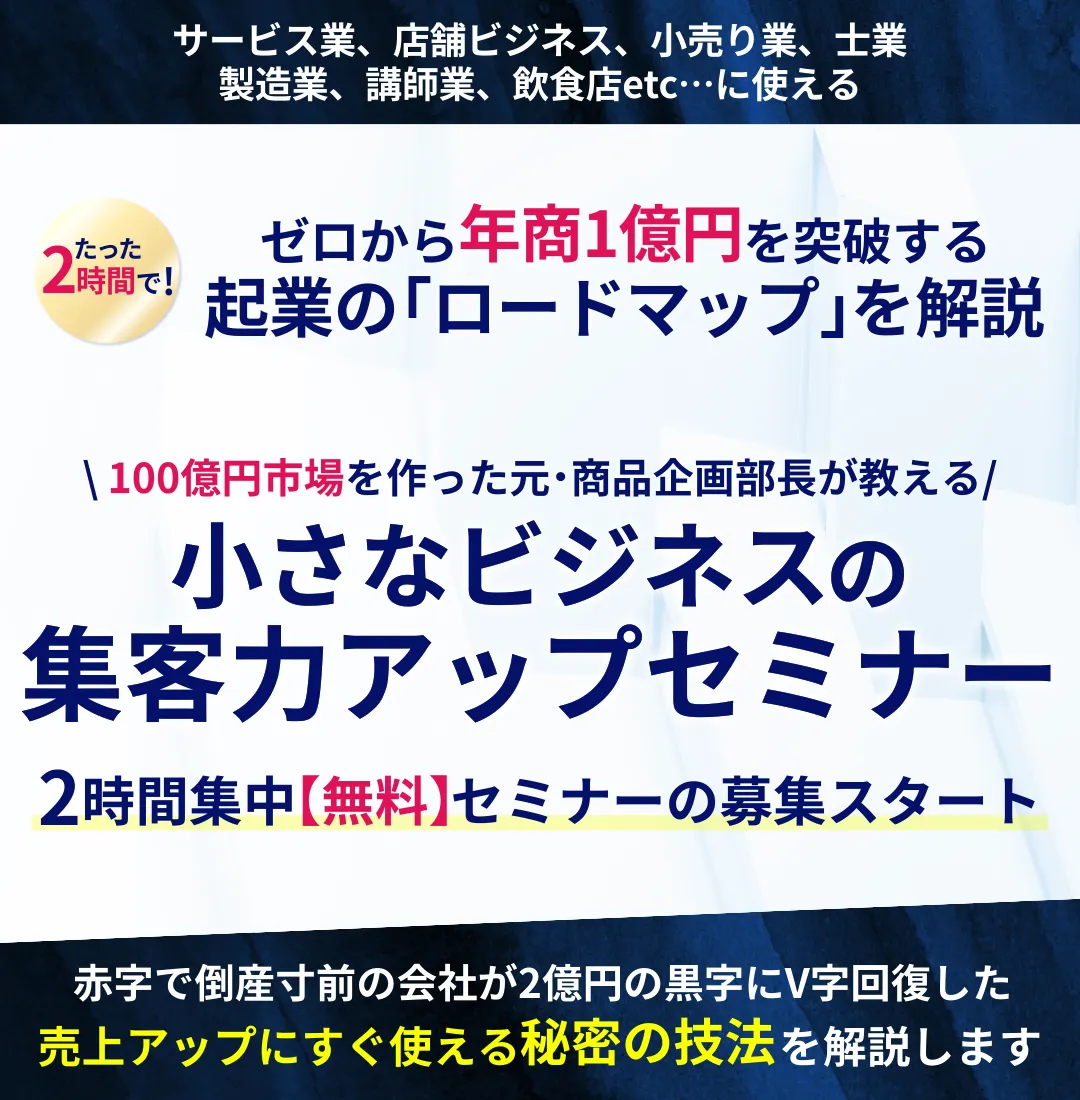
薄利多売はだめ?薄利多売のメリット・デメリットをわかりやすく解説
- 薄利多売の逆は何?
- 「薄利多売はNG」その理由が知りたい!
- 薄利多売で起業成功できる?
「薄利多売はダメ!」とよく言われますが、本当に薄利多売でビジネスは成り立たないのでしょうか。
実際には薄利多売でもビジネスは成り立ちます。
しかし「とにかく安くして、自分が頑張ればいい!」という気持ちでは、薄利多売のビジネスは失敗するでしょう。
今回は薄利多売というビジネス戦略の意味や、メリット・デメリットについてまとめていきます。
この記事を読めば「薄利多売」のビジネスが理解でき、起業を軌道に乗せる新たなヒントが得られるでしょう。
薄利多売とは?意味や対義語をわかりやすく説明


ここからは、「薄利多売」とはどんな戦略なのかをみていきます。
薄利多売の意味や、それを得意とする企業の特徴などを詳しく解説していきますよ。
あわせて、よく似た用語や対義語についてもまとめていきます。
薄利多売の意味
薄利多売とは、商品やサービスの1つあたりの利益を少なくして、数量を多く販売することで、全体の総利益を上げるビジネス戦略です。
例えばスーパーマーケットに買い物へ行くと、目玉商品としてお買い得な商品を店頭に並べているのをよく見かけますよね。
目玉商品は1つあたりの利益を少なくしても他店より安く提供することで、より多くのお客様を集客し購入してもらう薄利多売の戦略です。
大量仕入れやコスト削減を得意とする大手スーパーマーケットは薄利多売で、新しいお客様の獲得を狙っていたり、お店の知名度を上げリピート率を上げたりしています。
似ているけれど違う意味「多売薄利」とは
「薄利多売」は利益を出すために商品を安く大量に売るビジネスの「やり方」であり、「多売薄利」は商品をたくさん売ることができたが利益が出なかったという「結果」です。
「多売薄利」とは、商品は大量に売れているけれど、利益率が低いために結果として利益が少なかった、もしくは利益が出なかったという状態を言います。
漢字の並びが違うだけなので一見すると同じ意味の言葉と思われがちですが、2つの言葉は違った意味であることがわかりますね。
戦略的に利益を下げる「やり方」の薄利多売には前向きな意味合いが強いのに対し、不本意に利益が出なかった「結果」である多売薄利にはネガティブな意味合いが強い印象があります。
言葉と意味が混同してしまわないよう気を付けましょう。
「薄利多売」と逆のビジネスモデル「厚利少売(こうりしょうばい)」
「厚利小売」とは仕入れに対して価格を高く設定し、お客様に高い値段で買ってもらうことで利益を上げる戦略のことです。
「薄利多売」とは正反対の戦略で、価格の安さではなく価値の高さで商品を売る方法になります。
数で勝負はできないけれど、一つ一つの商品の価値を追求できる小売店や中小企業が、厚利少売を得意とするケースが多いです。
価格を高く設定するということは、商品に対しお客様が納得する付加価値をつけなければなりません。
高価格に見合うだけの高品質であることはもちろん、サービスを提供するのであれば人材育成、信頼されるブランドマネジメントが大切になります。
厚利小売が成功すれば商品を気に入っていただけるお客様に対して、品質を追求した形で提供することができるでしょう。
薄利多売のメリット3つ


起業をすると「薄利多売にならないように注意すべき」とよく言われますよね。
簡単な考え方ですが1万円を得るのに、100円商品を100個売るよりも、1,000円商品を10個売る方が商売としてはラクだからです。
薄利多売を成功させるためには効率的に商品を仕入れる施策やコストの削減の工夫、回転率の高い商品を選ぶなどの労力を要します。
ここでは、労力をかけて得られる薄利多売のメリットを3つ紹介します。
具体的にどのようなメリットがあって薄利多売を利用するのかを知りましょう。
メリット①売上を伸ばしやすい
同じような商品を購入するなら、少しでも安い方がお客様にとっては嬉しいですよね。
薄利多売では価格を低く設定するため、他に同じ商品を扱うお店より価格競争において優位に立てます。
「他店より安い!」というウリは一定数のお客様に刺さりやすく集客力が上がり、売り上げを伸ばすことにつながるのです。
また、大量の商品を売るためには回転率の高い人気商品などを選定しますよね。人気商品は需要が高いためすぐ売れることから、売上を増やせます。
さらに、お客様は低価格で商品が購入できることで、高い満足感を得られますよ。
その結果「また来よう」「ほかの人におすすめしよう」といった気持ちになり、リピート購入が増え、さらなる売り上げにつながるというサイクルが生まれるでしょう。
低価格なことでより多くのお客様を集客でき売上につなげやすいのが、薄利多売のメリットです。
メリット②キャッシュフローが安定する
回転率の高い商品が、薄利多売によって売り上げを上げることで、短期間で商品が現金化できることから、キャッシュフローが安定します。
キャッシュフローとは、ある一定の期間のうちにお店や個人が実際に受け取った現金と、支払った現金の流れで、お店が適切に運営できているかを把握する指標のことです。
仕入にかかった資金の回収が早くでき、手元に現金が残る状態が続けば、運営資金の支払いができなくなる資金ショートを起こしにくくなります。
ただしキャッシュフローの安定は、「薄利多売の回転率が高く、不良在庫が少ない」という特徴が実現できていることが前提です。
お客様のニーズに合った商品の販売で、経営を安定させられることで、リピーターの獲得やお店の信頼の獲得へとつながっていくでしょう。
メリット③顧客数が増えるのでリスクの分散ができる
大量の商品を販売できれば、それに比例して購入者が増えるため、少しお客様が減ったとしても、その影響が少なくて済みます。
例えば、100円の商品を売り上げ1万円にするためには、100人の購入者が必要です。1000円の商品なら1万円を売り上げるために、10人の購入者が必要になります。
しかし、何らかの事情で購入者がそれぞれ5人減ったとすると、以下のようになります。
- 100円×95人=9500円(-500円)
- 1000円×5人=5000円(-5000円)
同じ5人でも、購入者が多い100円の商品のほうが、お客様が減ったとしても売り上げの減少が少なくて済みますね。
実際の状況ではこのような単純な計算にはなりませんが、大量に販売することでリスクを抑えられることがわかりますね。
薄利多売では、購入者が減ることで起こるリスクを軽減できるのがメリットです。
薄利多売のデメリット3つ


薄利多売は売り上げを上げやすく、リスク分散も出来るビジネス戦略だとわかりました。
しかし表があれば裏があるように、薄利多売にはデメリットや一定のリスクも伴います。
これから、薄利多売のデメリットを3つ紹介します。
メリット・デメリットをしっかり押さえたうえで、自分のお店にあった形のビジネスを進めていきましょう。
デメリット①集客力をあげるための労力が必要になる
薄利多売では数量を多く売らなければならないため、集客力が大きなカギになります。
集客力を上げるためには、広告やキャンペーンなどの販促活動を行い、より多くのお客様の来店のきっかけをつくる努力が必要です。
集客力を上げるための労力は、宣伝費や人件費にダイレクトに影響してきます。そのため資金力のない企業は、薄利多売が難しいケースが多いでしょう。
また、たくさんのお客様に購入してもらうには、多くのお客様の満足度を上げる必要があります。
お客様の満足度を上げるためには、品質の向上、親切なサービス、接客、購入後のフォローなどを充実させる必要がありますよ。
ひとり起業で全てをあなたが担っている場合は、薄利多売で疲弊する可能性が高いことがデメリットです。
デメリット②赤字になる可能性が高い
利益の少ない薄利多売には、赤字になるというリスクが常に伴うこともデメリットです。
原材料や生産にかかるコストをしっかり管理できていない場合、利益を出せず赤字になってしまいます。
わずかな原材料の高騰であっという間に赤字に転じることもあるので、支出を下回らないような価格設定を意識しておこないましょう。
さらに、販売量の見通しをたて、需要に合った仕入れや生産をおこなう必要がありますよ。
需要を過小評価すると、在庫が足りず、売れるはずの商品の販売機会の損失になります。
逆に過大評価すると、売れ残りが在庫となり、在庫である間は利益にならない状態になってしまうのです。
コスト管理、需要予測のどれもが合致しないと、薄利多売で利益を出すことは難しいのがデメリットです。
デメリット③お客さんの求める価値が「安さ」だけになりやすい
安さに特化したのが薄利多売ですが、安さだけを求められがちになり、値上げなどで顧客離れを起こしやすくなるのがデメリットです。
「安さ」を追求することで、品質にコストをかける余裕がなくなってしまった場合、品質の低下や耐久性のトラブルなどにより、お客様の満足度が下がる可能性が高いですよね。
お客様は商品やサービスの価格以外のところに魅力を感じないため、値上げの際には「よりお得な他社」へと離れてしまうリスクがあるのです。
みなさんも、良いと思うものを人におすすめしようと思ったら、価格に見合った品質やサービスであるものをすすめたいですよね。
「安さ」のみの追求には注意し、品質や付加価値、お客様の満足度など他の要素もバランス良く考慮する必要があります。
商品の価値と価格をしっかりと見極めた上で「安さ」以外の強みを決めておくと、やむを得ない値上げに対しても柔軟に対応できるでしょう。
薄利多売で価格だけを重視するお客様を増やしてしまうと、関係を維持しにくくなってしまうので注意してください。
もしも値上げが必要な際は理由をしっかりと伝えると、お客様のお店への信頼感へとつながりますよ。
こちらの記事に、お客様の信頼を得る値上げの伝え方を具体的にまとめてありますので、参考にしてください。
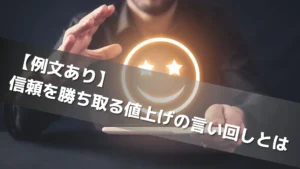
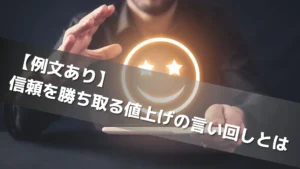
薄利多売で成功するためのコツとは?


リピーターは、定期的な来店が見込めるだけでなく、購入単価が高く経営を安定させてくれます。
リピーターを増やすことで、集客に労力やコストをかけず売り上げを上げることができるようになるため、積極的にリピーターの獲得に力を注ぎましょう。
先ほどのデメリットにもあったように、「安さ」のみの追求では薄利多売は行き詰ってしまいます。
品質やサービスを工夫し、安さ以外の付加価値を付けることは、競合品との差別化を図り、競争に負けない力をつけるために重要です。
リピーターの作り方はこちらの記事で詳しく紹介しているので、あわせてチェックしてください。
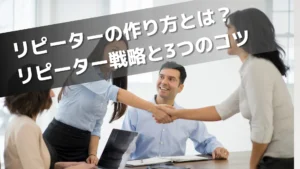
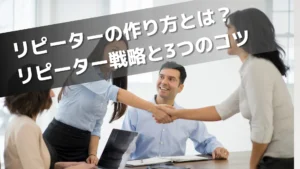
まとめ
この記事では、薄利多売について紹介しました。
記事の要点を簡単にまとめます。
- 薄利多売は、売り上げが上げやすく、短期間で商品が現金化できる
- 薄利多売でキャッシュフローが安定し、資金ショートを起こしにくくなる
- 薄利多売で購入者が増えることで、お客様が減ることへのリスクが軽減される
- 薄利多売のデメリットは、価格設定やコスト管理を誤ると、赤字に転じやすいこと
- 薄利多売を成功させるためには、集客によるリピーターの獲得が必須
- 薄利多売では品質や利益の範囲内で付加価値を演出し、顧客離れを起こさないよう注意する
- お客様にとってお得と感じる特典で差別化を図り、競争に負けない力をつけることが大切
今の事業が充分な利益率を確保できているのであれば、薄利多売によって、売り上げアップや収支の安定、リピーターの獲得にとても有効な手段となるでしょう。